「異世界転生モノ」についてのエッセイ─19世紀植民地ロマンスとの対比から
作品のアニメ化などで話題になっているサイト、『小説家になろう』では多くの「異世界転生モノ」が見られる。これらのテンプレートは、「異世界転生して現代知識で『チート』をし、異世界を発展させるとともに現地の少女たちと恋愛をする」といった具合だ。
私は、この「異世界でチートをする」という構造は現実の植民地主義の比喩であると私は考えている。文明の劣ると考えられたアフリカその他で自国の文化や文明を伝えて、「啓蒙」する。この図式は実に爽快である。何と言っても自国の優位性が明白であり、愛国心─愛する自国の優位性から来る圧倒的満足も含め─を満たせるのだ。そして現地の少女─彼ら植民地支配を行う側からしたら絶対的に弱者である─を手篭めにする。まさしく植民地政策真っ只中の西洋諸国の夢やロマンス願望を煮詰めたものであるのだ。
日本は朝鮮半島を植民地支配したが、「西洋の植民地の本場」であるアフリカ大陸ではそれは叶わなかった。まるで(果たせなかったアフリカ大陸での)植民地願望を異世界で充足するといった具合だが、とにかく異世界でチートものはこのような構造を感じてしまう。
ところで、このような植民地支配と関連する恋愛ものは英語圏では「colonial romance(植民地ロマンス)」と言われて一定の需要がある。文字通り植民地での恋愛を描くものであり、現地人と(あるいは現地人同士が)恋愛するものである。この植民地ロマンスの日本版が異世界でチートものなのだ、という直接的な考えは宜しくない。なぜなら欧米の植民地ロマンスは当初から反キリスト的要素を持っていたからだ。どういうことかというと、かつてキリスト教規範が強かった時代、恋愛自体が社会ではタブー化されていた。恋愛結婚の誕生はごく浅い歴史なのである。恋愛結婚は社会から禁止されたタブーであり、実際好まれなかった。このような閉塞感の中、植民地というキリスト教規範が完全には到達されていない地を理想化し、そこで恋愛させるという小説が流行ったのだ。
(19世紀)恋愛は教会と結婚の制度に対立するものであった。つまり、反社会的なものであった。反社会的なものであるために、恋人たちはあるいは逃亡を余儀なくされ、あるいは避難所を求める。*1
反社会的な恋愛を唯一満たせるのが植民地であった。植民地で現地の男女と恋愛し、キリスト教規範に縛られずに自由にロマンスに満ちた生活が送れる。そこにタブーなどはない。このような結果として、植民地ロマンス小説は大流行したのだった。
さて、日本ではどうだろうか。確かに日本でも恋愛結婚は稀だったが、キリスト教規範という宗教的タブーがあった西洋よりもそのタブーの度合いは低かったのではないか。結論を先に言うと、日本で流行りの異世界転生モノは「植民地での恋愛」を描く点では古くからある植民地ロマンスと同じであるが、反社会的・反教会的要素を持ち合わせていないのである。どこか背徳的要素があったかつての植民地ロマンスと違い、異世界転生ものでは実に恋愛に積極的である。
現代における異世界転生はタブーなき植民地ロマンスと捉えることができる。植民地ロマンスの要であったタブー要素は異世界転生には見当たらない。21世紀という、植民地ロマンス全盛期から数百年経った現在ではもはや背徳感や反社会的要素という要は不要どころか害悪なのかもしれない。恋愛結婚というのはごく最近生まれた概念だが、もはや当たり前のように我々の生活に根付いている。もはや恋愛結婚という概念自体が、そこまで持て囃されるものではなく、「当たり前」であり、殊更それを大袈裟に騒いだり作品のテーマに据える必要が無いのであろう。
ここまでをまとめると、異世界転生で「異世界」で「チート行為」をしたり現地で恋愛するのは植民地ロマンスと同様(この場合「異世界」が「植民地」になる)だが、その要のタブー要素がないのである。それは21世紀という恋愛結婚の幻想が支配的になった現代では必然なのかもしれない。異世界転生モノの話題を聞くたびに私はこのような植民地との構造や植民地ロマンスを思い出してしまう。皆さんもたまには世界転生モノを、植民地ロマンスの懐かしい時代を創造しながら読むと面白いかもしれない。古今東西、人類は異世界(植民地)でチート行為をし自らの愛国心を満足させ、女性を手篭めにし、更には(西洋においては)恋愛という反社会的行為への背徳感を味わったものなのだから。
※作品を晒し上げる意図はないため、具体的作品名を出さずに語りましたが、そのせいで分かりにくくなっており、申し訳ないです。
イギリス料理はなぜ「まずい」のか─産業革命と二度の大戦から
このブログ記事は下記のエントリーの補足ですので、ぜひ下記のエントリーもお読みください
1.はじめに
イギリス料理=まずいというステレオタイプは日本において根強く有る。ツイッター、mixi、2ちゃんねる…あらゆるところで毎日のようにネタにされる。しかしなぜイギリス料理はまずいのだろうか。ここではイギリス料理がなぜまずいと言われるようになったかを簡単に論及していきたい。
2.産業革命以前の料理
14世紀に書かれたイギリス料理のレシピ集『The Forme of Cury』を見れば数多くの料理がいきいきと書かれているのに気づくはずだ。当時まだ貴重品だった砂糖も1/3の料理に使われるなど非常に豪華なメニューが載っている。加えてナツメグやクローブなどの香辛料もふんだんに使われているなど「先進的」なレシピも多数あった。また、イギリスには中世以前から続く豊かな食文化があった。800年頃に開発されたブラック・プディングは血を入れたソーセージで独特の味わいがある。13世紀年頃のパスティは牛肉や玉ねぎを入れたいわばパイで、具材から出るエキスの香ばしさとサクサクとした生地を楽しめる。スコッティーケーキはケーキという名前に反して、重量感のあるパンだが、中に色々な具材を入れることで多様な味を生み出している。シチューはどの国にも有る伝統料だがイギリスにも存在し、うさぎの肉を使い香辛料で臭みを消したスパイシーな料理方法が残されている。

(伝統的パスティ)
このようにイギリス料理は決してネットで吹聴されるような「ただ茹でただけの野菜」を出すような貧相な食文化ではなく、気候故に取れる野菜は少ないものの、現地で入手できる様々な食材と輸入される希少な香辛料などを使って豊かな食文化を作り出していたのがわかる。
この食文化の拡充は18世紀まで順調に続く。17世紀の料理本『Cooks Guide』ではフランス料理の影響も垣間見え、フランス料理の命とも言える「ソース」のレシピをイギリス流にアレンジしたものが乗っている。18世紀になってもジェームス・ウッドフォードの『Diary of a Country Parson 』によれば、チキン煮や甘いケーキにブラン・マンジェ、アーティチョークを大いに食べ、加えて食後に果物を食べたという旨が乗っている。つまり確実にここまではイギリス料理は順調に発展を遂げていたことがわかる。この時期、伝統的料理にフランスなどの大陸に影響を受けた料理まで様々な料理が存在した。もちろん、庶民は新しい料理(特に香辛料を使ったものなど)は気軽に楽しめなかっただろう。彼らは身近にある素材で作れる中世以来の伝統的料理が主だったのは忘れてはならない。いくつかの旅行記に「イギリス料理はまずかった」という記載*1があるにしろ、この時点では順調に発達してしてきていたのだ。庶民の伝統的料理にも胡椒が使われるなどささやかな変化があっただろう。しかしこの図式が崩れるのが産業革命期、そうヴィクトリア朝である。
3.ヴィクトリア朝による料理の衰退
産業革命期はイギリス料理のその後を決定づけた。一体何が起こったのだろうか?
まず産業革命期と同時に起きたエンクロージャー(囲い込み運動)*2である。この動きは大きく第一次と第二次に分けられる。特に第二次エンクロージャーは食糧増産のために行われたが、この結果イギリスの穀物生産量は増大した。一方農民は農地から追い払われて都市生活者となりこれらが工場労働者の母体となった。かつて農民は農地と隣接してある森林を使って様々な生産活動を行えた。例えばヨーロッパ全域で広く行われた共有地である森林に豚を放して豚に落ちているどんぐりなどを食わせて肥え太らせ、冬前に解体することで冬季の食料にするなどである。また、森林では野鳥などを捕まえることもできた。加えて農村に流れる川、または海からは魚介類を得ることもできただろう。エンクロージャーによって無理やり都市部に追い払われた農民はかつてのように無料で畜肉を手に入れるのが不可能になった。このため僅かな金銭しか得られない下層市民達は肉を食べるのは非常に稀な機会となってしまった。
産業革命はこのような農村から出てきた農民を工場労働者として働くことでなりたっていたが、前述したようにこのような市民は僅かな銭しか得られなかった。彼らが買えるのは低価格なじゃがいも、ストリートセラーが売る低価格の出し物であって、ここで伝統的な農村(=森林からの恵みを得られる)と密接して成り立っていた料理は崩壊した。例えばブラック・プディングなどはかつては自家製で各村で作られていたが、ヴィクトリア朝期には購入するしかなくなり、次第に市民は口にする機会が減ったことだろう。また、ヴィクトリア朝期には生きていくためには家庭全員で働く必要があった。彼らは十分な初等教育も受けぬまま、また今で言う「家庭科の知識」=料理の知識を得られぬまま育っていった。加えて当時薪の枯渇から燃料費は増大の一歩となっていた。このために調理方法も凝った方法はできずに、沸かした湯で短時間じゃがいもを茹でる、などのシンプルな料理方法にならざるを得なかった。このような結果として、産業革命の到来とともに中世以来の豊かなイギリス食文化は崩壊を迎えたのであった。
ここまでを約言するとエンクロージャーによって農村を負われた農民は都市の工場労働者となった。彼らは幼いうちから働く必要があったたために充分な料理の教養を得られなかった。加えて森林からの恵みを得られないことによる食糧費の増大は家計を圧迫し食材の品質や品数を低減させ、燃料費の増大は調理方法までシンプルなものにせざるを得なくなった。これらの事情からイギリス料理は我々がステレオタイプで知っているような「ただ茹でる」「ただ焼く」だけとなっていったのである。
このような「茹でるだけ・焼くだけ」の極地がネットで盛んに話題にされるウナギのゼリー寄せである。そもそも魚のゼラチンを利用したゼリー寄せは世界各国にあり、ことさらイギリスにおけるウナギのゼリー寄せだけをネタにするインターネットの動向はどうかと思うのだが、とにかくウナギのゼリー寄せはうなぎをただ茹でただけの料理であった。私見であるが、この料理は「意図的に固まらせた」というよりストリートセラーなどが道端でうなぎを茹でたのを売っている内に、冷えて勝手にうなぎとその煮汁がゼリーのように固まってしまったのが本当の例だと思われる。ストリートセラーが売る「ただ茹でた」「ただ焼いた」ものは他にも有り、牡蠣やじゃがいも、魚介類などを茹でたり焼いたりして売っていた。

(ウナギのゼリー寄せ)
これらの事情の他にも食材の偽装も食文化の衰退に拍車をかけた。先述したブログに書いてあるように当時のイギリスは食品偽装のオンパレードであり、あらゆる食材が有害な化学物質、あるいは無害だが不衛生的な混ぜものに汚染されていた。これらの食材は低価格だったため、労働者が必然的に頼るようになりこれも料理の味の低下を齎したであろう。
これらのヴィクトリア朝期の食文化衰退は、中流階級までもを襲った。そもそもイギリスの上流階級はフランスなどの料理人を雇って、フランス流の料理を熱心に食べていたが、新興した中流階級も上流階級の真似事として料理人を雇ってその料理を食べるようになった。しかし中流階級が雇える使用人というのは労働者階級の出の貧しい少女や少年であって、今まで述べてきたように彼らは料理の教育を受けてこなかった。彼らが作れる料理というのは労働者階級の料理─ただ茹でる・ただ焼く─だけであって、結果として中流階級も我々から見たら貧しく・美味しくない料理を食べていたことになる。いずれにしろ、農民などの口伝でつたわってきた豊かなイギリス食文化はここで一度の崩壊を迎えることになった。
ここで疑問が浮かぶ方も多いのではないか。「なぜ産業革命をした国でイギリスだけが食文化の崩壊に至ったのでは」と。ここで、『エコノミスト』のコラムではこう答えている。「工業化の前に、彼はイギリスの料理はヨーロッパで最高だったと主張する。しかし、英国が工業化する最初の国であったため、冷蔵庫はまだ発明されていなかった。このように、英国人は現代の食料保存技術の恩恵を受けずに農場を去ることになったのだ。彼らは食材の策源から遠く離れて、缶詰の野菜、保存された肉、根野菜などに頼って、少なくともこれらを魅力的なものにするために揚げたのだった。技術によって新鮮な果物や野菜が利用可能になった後でさえ、英国人の口の中は軽くて脂っこい食事に設定されていた。」*3つまり、イギリスは産業革命が最初の国だったために発達した食料保存技術の恩恵を受けられずに、缶詰の野菜や干し肉などしか手に入れられなかったとしているのである。もし食品保存技術でより安価により質のいい食材がイギリスより遅れて産業革命が到達した各国で手に入ったのならば、その分だけ食文化の崩壊は避けられることになる。加えて、イギリスのように深刻な燃料不足が併発して起こっていなければ更に食文化崩壊の危険性は低くなるのである。「産業化の時代には、世界が持てるものと持たざるものにはっきりと分かれていた。工業化社会では食料供給の問題は解決された」*4というようにイギリスより後発に産業革命を迎えた国は食料供給の問題を解決していたのである。もっとも、個人的にはどの国も産業革命によって農村から切り離されたことで食文化の少なからぬ崩壊は訪れていると思われる。程度問題というわけである。
4.さらなる苦難─第一次世界大戦と第二次世界大戦
ヴィクトリア朝期に食文化の崩壊が始まったとは言え、徐々に労働者の地位や給与が増大してくるに従っていくらかの改善が見られるようになった。それは1845年に初版が刷られ、ベストセラーとして20世紀まで重版が重なった『Modern Cookery for Private Families』などでも伺える(もっともこの本が刷られた当時の労働者にはこのような本を読む技術も、買うお金もなかったのだが。この本が労働者階級に流行りだすのは20世紀にはいってからである。)。
20世紀に入ると、労働者の待遇も改善され、燃料費の増大も落ち着き、また食品保存技術の拡大で新鮮な野菜や肉や魚が簡単に手に入るようになっていった。これに伴って、多くの料理本が発売されるなど食文化の崩壊は一旦歯止めがかかったに見えた。
しかし、そんなイギリスを待っていたのは第一次世界大戦と第二次世界大戦であった。第一次世界大戦はドイツの食糧不足が有名だがイギリスも少なくない食糧不足に悩まされた。かつて食卓を彩っていた様々な野菜や果物、肉類などは姿を消して再び粗雑で簡単な料理─さながらヴィクトリア朝期のように─にならざるを得なかった。この苦難は第一次世界大戦終了後の戦間期には改善されるが、すぐに第二次世界大戦がやってくるのである。第二次世界大戦ではバナナ、タマネギ、チョコレートなどの食べ物は市場から消え、乾燥卵、乾燥ジャガイモ、クジラの肉、スパム(缶詰)、snoekと呼ばれる「嫌な」輸入魚などの珍しいものが食卓に現れた。バター、砂糖、卵、小麦粉は欠乏し、パイやケーキなどの英国料理は伝統的なレシピで作ることが難しくなった。結論として、この時期は我が国で太平洋戦争中に代用食材が流行ったように代用品が横行し、著しく料理のクオリティは下がることになった。この時期にイギリスに駐留したアメリカ兵などはイギリス料理はまずいと感じ、本国に帰ってそれを広めたであろう。現代的な「イギリス料理はまずい」というステレオタイプは根源的にはこの時代の料理から来ているのだと予想される。

(WW2中イギリスで配給された缶詰の中でも最も有名なスパム缶)
結果的に、イギリス料理は何度も崩壊を迎えた。まずはじめにヴィクトリア朝期、次に第一次世界大戦、最後に第二次世界大戦である。この期間にイギリスを訪れた者たちが口にした料理は今の我々が偏見抜きに食べたとしてもまずかったに違いない。このときの風評が今になってもステレオタイプとして保存されているのである。
5.イギリス料理の再生と進展─第二次世界大戦終結後
第二次世界大戦後、しばらく経つとまた食文化は再生をし始めた。手に入らなかった新鮮な肉や魚、卵などは輸入品を取り入れたこともあって市場に流れ始め、イギリスは再び伝統的な料理を作れるようになった。それだけではない。世界中が流通網で密接に結ばれ、新たなイギリス料理も誕生し始めた。今までは自国で生産できなかった数々の野菜や魚などを利用した新しい料理である。もともと植民地を通じて得ていた多文化主義的料理も更に飛躍を遂げ、多くのバリエーションを生み出している。もはや我々が知る「まずい」とされるイギリス料理は過去のものとなりつつ有る。海外のフォーラムに寄せられたコメントを引用して言えば「(イギリス料理の)ステレオタイプを受け入れないでください。英国に行き、料理を自分で試してみてください。あなたは失望しませんよ」*5ということだ。食文化は常に発展する。逆風によって挫けようと時が経てば、また逆風が止めば、また回復・進展するのである。現代のイギリス料理の美味しさはまさにこれを物語っているのである。

(現代的イギリス料理、「ホワイトハート」。各国から輸入される食材で構成されている。)
6.おわりに
ここではイギリス料理の簡単な歴史となぜ美味しくなくなったかを簡潔に論じた。産業革命期に衰退したイギリス食文化であるが、他国の食文化も産業革命期にどのようになったかは気になるところであるが、私は外国語の才がなく、ドイツ語やフランス語を理解できる方にぜひ研究してほしいところである。日本の食文化も戦後一旦崩壊しているので(そばなどがいい例である)、そこと比べてみるのも興味深いだろう。
この短い論考でぜひイギリス料理への偏見がなくなれば嬉しいところである。料理はアイデンティティであり、民族の誇りである。その誇りやアイデンティティをステレオタイプで雑に語って言いわけがない。みなさんもぜひイギリスに飛んで、または日本の専門料理店で現代の、または伝統的なイギリス料理を味わってみてください。
*1:『生活の歴史10 産業革命と民衆』にもそのような文が記載されている
*2:囲い込み運動とは農民の解放農地を取り上げ、そこに柵を立てて=囲い込みし、羊などを放すことである。第一次は地主によって行われたが、第二次は政府や議会主体で行われた。
*3:http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2006/12/british_food
*4:フェリペ・フェルナンデス=アルメスト著『食べる人類誌』
*5:Why is British food often perceived to be terrible? - Quora
ヴィクトリア朝庶民の暮らし
1.はじめに
一般的に優雅で安泰のイメージが持たれる─『シャーロック・ホームズ』や漫画の『エマ』などがいい例である─ヴィクトリア朝イギリス(19世紀-20世紀初頭)であるが、その実庶民の暮らしは過酷そのものであった。我々はどうしてもメイドや執事、そして貴族などの華やかなイメージを持ってしまうが、その裏腹に食品偽装は横行し、産業革命によって花開いた近代的労働は殺人的領域まで達していた。本稿ではヴィクトリア朝イギリスにおける庶民の暮らしにスポットライトを当て、簡潔に解説していきたい。
2.横行した食品偽装について
食品を保護する法律などがなかった当時、食品偽装は大変大規模に行われていた。代表的なのがコーヒーや紅茶などであるが、その他の食品の偽装も盛んであり、高い安全な商品を買えない労働者は常に食品から有害物質を摂取する危険性にさらされていた。
a.コーヒー
コーヒーにおける食品偽装の大半はチコリーによるものであった。我々の身近ではコカ・コーラ社の爽健美茶に含まれている。つまり、コレ自体は有害なものではなかったが、多くの店で「コーヒー」として売られている製品のうち、本物のコーヒー豆は1/2以下であり、また混ぜ者入りの表記はなされていなかった。中には炒った小麦が混入されている場合もあった。

(チコリー入りのコーヒー)
b.紅茶
イギリスが誇る紅茶にも不正が行われていた。多くがグラファイト、プルシアンブルー色の顔料、ウコン粉、およびチャイナ粘土であって着色されており、これらは人体に有害なものもあった。「着色に使われる物質はしばしば高度に有毒であって、多くの場合にシナ人が使っているものよりもより反対すべきであるし有害である。」*1また、「紅茶」自体が。お茶の葉からできているのではなく身近で手に入る雑草などの場合さえあった。
c.黒砂糖
砂糖は多くの製品がダニ、カビの胞子、石、砂で汚染されていた。穀物の粉が混入されている製品もあり、これはかさ増しのためであった。

(砂糖中のダニ)
d.野菜
大半の野菜が銅で汚染されていた。「(検査した野菜のうち)27標品は多かれ少なかれ銅が沁み込んでいた」*2。加えてこれらの銅汚染は深刻なものもあった。これらの銅は野菜を新鮮で「いい色」にするために使われていた。
e.砂糖菓子
多くの菓子が有害な金属による無機顔料で着色されていた。多く使われていた色は黄色、ピンクと緋色を含む赤、褐色、紫、青色、および緑色であった。加えて、砂糖のかさ増しのために硫酸カルシウムが広く用いられていた。
f.ビール
ビールの不正の多くは水を加える水増しであった。この処理のために風味がビールから損なわれる事となるが、それを隠すために粗悪な砂糖(粗糖)を混入している例が多かった。この処理でビールの度数は約半分となっていた。
g.たばこ
タバコの不正はタバコ以外の葉を混ぜることで行われていた。また、嗅ぎたばこの場合は鉛を加えている場合もあった。鉛の混入は非常に悪質かつ広範囲で行われており、鉛中毒を発症する場合さえあった。
3.過酷な労働環境
労働者階級は閉鎖的で堅固な社会構造のように見えるものの、独自の排他的な世界を構築していた。これらの試みの意味は一部は、現実世界の過酷さからの脱出であり、一部は工業都市の匿名コミュニティを作り出すものだった。究極的には、教育と民主主義の発展、生活水準の向上、労働条件、住居、食べ物や服装によって、労働者階級は社会の参加者になったが、ほとんどの期間[1820 -1920]彼らは政府が高らかに謳う「公的生活」から除外されていた。
a.ストリートセラー
ストリートセラーは路上で何かを売る人たちを指した言葉である。1800年代後半には、おそらく約30,000人のストリートセラーがロンドンにいて、それぞれが手押し車やカートから商品を売っていた。売っているものはカキ、ウナギ、エンドウ豆のスープ、揚げた魚、パイとプリン、ピクルス、ジンジャーブレッド、焼き芋、クランチ、咳止め、アイス、ビール、ココア、ペパーミント水だけでなく、衣類、中古の楽器、本、生きている鳥などでさえあった。破損した金属、ボトル、骨や水切り、壊れたろうそく、シルバースプーンなどの「台所用品」などの廃棄物を購入する業者も存在した。

(アイスを売るストリートセラー)
b.マッドラーク
「Mudlark」と呼ばれる人たちはテムズ川の汚泥の中から物品を回収し、売る仕事である。金品はもちろんそのまま売ることができたし、他の一見役に立たなそうなものも買い取る専門業者が存在した。より良いものを求めるために深いところまで足を踏み入れ溺死する者もいた。また、テムズ川は大変汚染されており、これも危険な職業であった。

(Mudlarkを描いた絵)
c.ワークハウス(救貧院)
新救貧法発令から特にそうだが、救貧院は貧困者を収容するいわば「貧困層の収容所」であった。ここでは単純労働を主に収容者に課していたが、それらは花崗石を砕く、糸を紡ぎ続けるなどの「技能もいらない仕事」であって、収容者の自立には繋がらなかった。家族が救貧院に収容された場合、もう一度会う手段はなく、陸の孤島と化していた。職場の食事は、飢えから守るだけの程度のものしか出されなかった。衣服もときどき洗われる程度のものだった。子どもたちは何らかの初頭教育を受ける権利があったが、これはしばしば職場の看守によって無視された。

(「棺のベッド(coffin bed)」で寝る救貧院の収容者たち。キリスト教圏であるイギリスでこのような棺で眠るという行為は、非キリスト教圏の我々が想像する以上に悪い意味があった。)
d.港湾労働
造船所やロンドンと北東部の新しい港湾では巨大な労働力が必要だったが、需要は予測できなかった。毎朝、数ペンスで1日の作業を行うために集まる男性達が見られた。需要が不規則なため、造船所が注文不足や苦しい天候によってたびたび閉鎖され、慈善団体もなかったため、労働は不規則でこれだけで食べていくのは不可能であった。

(日雇い労働のために集まる労働者)
e.売春
多くの女性が売春をしていたのは驚くべきことではなかった。ロンドンのスラム街の通りには売春婦が住んでいた。売春を行う少女らは性感染症によって早死していった。大きな病院のいくつかは性病治療専門の病棟があったことからその規模が窺い知れる。しかし当時最も恐ろしい性感染症の梅毒の治療法は知られていなかった。W.T.ステッドが13歳の処女を簡単に路上で買えたという報告をしており、売春がいかに低年齢で、広範に行われていたかを物語っている。
f.児童労働
ヴィクトリア朝の「一家族」は子沢山であり(その分多くの子供が餓死や病死した。多産多死であったのだ。)、その分「要らない子」も数多く発生した。そんな彼らを「雇用」したのが児童労働であった。Climbing boyと呼ばれた子供の煙突掃除夫は、子供というサイズを活かして煙突に潜り込んだが、煙突から燻る煙で焼死・窒息死することも多くあった。Crossing-sweeperと呼ばれた子供の路上掃除夫は路上に溢れるゴミ、汚物を掃除する仕事であった。子供ゆえの小ささを活かして、鉱山の小さな洞穴でトロッコ引きをする子供らもいた。彼らはこれらの労働で貧しい家計を支えたが、児童故に得られるのは僅かな小銭であり、仕事によっては死亡率が大人の数倍にも登った。

(業者に子供を売り渡す貧困家庭を描いた図)

(鉱山でトロッコ引きをする少女)
g.社会保障
労働者が雇用を失ったとき、彼らは友好的な社会、労働組合、労働組合、地元の店主、その隣人や友人、牧畜業者、または貧困者の法律に基づく信用組合による補填があり、これは現在「社会保障」と呼ばれている唯一あった 。彼らが老後になったときや虚弱になったときには、先の信用組合は生活費の一部しかカバーしていなかったため、子供の助けがなければ生活していけなかった。政府の社会保障が事実上完全に欠如しているという事実は、今の我々から見たら理解不能であると思われる。
この他にも数多くの労働が存在したが、労働規制などない時代故にどれも過酷な労働であることは変わりなかった。搾取労働も盛んであり、女性を「お針子」として長時間拘束し、たった数ペンスの稼ぎだけで労働させるような「搾取工場(sweatshop)」が存在するなど、労働者の身分はいまと比べて著しく低かった。
4.ヴィクトリア朝の生活
a.家庭での食事
ヴィクトリア朝は英国の伝統の食事が破壊された時期であった。農村社会から切り離された労働者達は子供の頃から働き、料理を覚える暇など無く、かつ燃料が高騰していたのもあって凝った調理法はできず、単純な「茹でる」「焼く」程度しかできなかった。調味料の値段も高く、必然的に塩味だけの茹でたじゃがいもだけという料理が横行し、英国伝統の食事は労働者たちからは失われた。
b.医療・衛生
医療は19世紀に多く邁進したが、その恩恵に預かれるのは医者にかかることができ、その時間も有る中流階級以上のものだった。下流階級では多くの民間医療が残っており、「バターと蜘蛛を一緒に食べる」などの根拠不明な医療が行われていた。衛生状態も悪くジョン・スノウの調査によれば、下水道が流入したテムズ川下流の企業から水を購入した家庭が、下水道が流入してない上流にある会社の水を買う人より14倍も(コレラによる)死亡率が高いなど、汚染は深刻なレベルであり、一般庶民は食生活のみならずあらゆる面で危険に接していた。加えて1875年の公衆衛生法で衛生状態を改善する試みが試されたが、初期の段階で恩恵を受けれたのはやはり中流階級以上であった。

(当時市販されていたランベス社の水の微生物を描いた図)
この当時の「医療」による麻薬汚染もひどかったが、それについては下記の記事を参照のこと。
c.余暇
悪いことばかりを述べてきたヴィクトリア朝であるが、そんななかでも庶民に娯楽は存在した。オルガンライダーと呼ばれた人たちはオルガンによって路上で演奏し、チップを貰っていた。このようなストリート・ミュージシャンは数多くおり、写真も残されている。また、鉄道の発達は庶民でも気軽に遠出ができることを意味しており、比較的裕福な労働者は夏の間海に行って遊ぶなどの行為もできた。
しかし、多くの貧しい子供たちはおもちゃや余暇のためのお金はなかった。彼らは路地を除いて遊ぶ場所はなかったし、仕事をしなければならなかった。だけれども、貧しい子供たちは幾つか楽しいことができた。彼らは見つけられたものは何でも活用し、川で遊んだり、樹木やランプポストに登るなどの「お金の掛からない」遊びをしていたと考えられている。

(1870年代に撮影されたストリート・ミュージシャン)
5.終わりに
本記事ではヴィクトリア朝の庶民の生活を紹介したが、この他にも多く語らなければならないことがある。それらはまた別の記事で紹介したい。メイドや執事のイメージで語られるヴィクトリア朝であるが、このように庶民にとっては非常に厳しい時代でもあった。その辛い暮らしの一部でも紹介できたらならば幸いである。
この時代にもっと興味があるならば、下記に上げたWebサイトは無料で閲覧できるのでおすすめです。
参考文献
・ハッサル・アーサー・ヒル『食品の混ぜ物処理』
・BBC - Primary History - Victorian Britain
・Victorian Occupations: Life and Labor in the Victorian Period
・ヘンリー・メイヒュー『ヴィクトリア時代 ロンドン路地裏の生活誌〈上〉〈下〉』
『けものフレンズ』7話から見る火と調理の神話学
1.はじめに
最近ネットでけものフレンズというアニメが流行っている。私もDアニメストアで視聴しているが、ユーモラスで可愛いキャラ、そのキャラ同士のやりとり、ほのぼのした(それでいてポストアポカリプスを匂わせる)世界観…いいところを上げればキリがないのだが、ともかくハマっている。そして、先日視聴した7話では料理がテーマの回でそ、の中で火の扱いが出てきた。この描写に私は深く感動し、その感動と解説をここに書き記すものである(大袈裟)。
2.火の意味するところ
まず火なるものの意味を考えたい。たいていの文化圏では火の神話が存在する。古代ギリシャにおいて火はプロメテウスが天から盗んだ火である。北米インディアンのダコタ族では最初の火は太陽であり、原始の闇にいた神々が太陽に火をつけたのだという。クック諸島では、マウイ神が地中深くに降りて火を齎した。オーストラリアのある原住民は、神聖なるトーテムの動物のペニスに火が隠されているのを見つけた。
つまり、火とは神や聖なるものからもたらされるものなのである。神話学では「誰にでもその人だけのプロメテウスがいる」という格言があるくらいのように、火とは恩寵的なものである。このように火は一種神聖なものであると同時に、貴重なものである。神話学者であるフレイザーはこのように言う。
ヴィクトリアの原住民族のいくつかは、一つの伝承をもっている。――火はできるだけ用心して使われなければならないが、それはグランピア山脈に住むカラスに独占されていた。そして、カラスは、火を非常に貴重なものに思っていたので、ほかの動物は、それを手に入れることが許されなかった。しかし、ユーロイン・キーアという一羽の小鳥――火の尾をもったミソサザイ――は、カラスがつけ木を振りまわして楽しんでいるのを見て、その一つをくちばしにくわえて逃げた。タラクックという一羽のタカが、ミソサザイからそのつけ木をとりあげ、国のあちこちに火をつけた。その時以来、火は常に、燃えつづけており、その火から、人間はあかりを得ている。*1
このように火は非常に大事なもので、神話には「火を盗む」というストーリーが数多く有る。具体例をあげればヴィクトリアの最南東部にあるギプスランドの神話などであるが、とにかく火は貴重であり、独占するほどの大事なものであり、神から与えられ、そして人の持つ火はその独占する何者からか奪取したものである。加えて、独占していたとされる動物は引用した事例のようにカラス、ミソサザイや雀など鳥類が多いのである。
では7話ではどうだったであろうか。サーバルちゃんは「火ってみつかった?」とかばんちゃんに尋ねる。「教授」と「助手」のミミズクたちは「火はおいそれと渡せない」という。つまりけものフレンズの世界において火は「探す」もの、「授けられるもの」であり、それを独占するのがミミズク=鳥たちなのである。これは神話における火を独占する鳥たちの構図をそのまま描いている。加えて、サーバルちゃんが火を探したように、けものフレンズ世界では火とは「着ける」ものではなく「既に授けられたものを使う」のであり、これは神からもたらされた火を使う(神話における)人類と同様である。彼女らにとって火は神のような存在から齎される神聖なものであり、自ら着火するという概念がないのである。「(彼らにとって)火はとても神聖なものだから、自分で起こすことなど考えられない」*2のである。実際、タスマニアやアンダマン諸島、ニューギニアの部族は火が消えると近くの部族を訪ねていき火を分けてもらう。神聖な火は起こすものではなく、「授かる」ものなのだ。
そして、動物たちは「神」たる自然から齎された火で調理する。
多くの動物は自然発火の残り火に集まり、焼けて食べられるようになった種や豆を探す。(…)充分な知能を持つ器用な動物にとっては、焼き尽くされた森林に特有の灰の山や燃え残った倒木の幹は天然のかまどのようなもので、噛み砕けない豆やかたくて噛めない肉を調理できたと思われる。*3
動物が火を恐れるというのは一種の空想もあるのだが、実際は自然発生した=神からの火を彼らは利用して、食べ物を食べるのに役立てている。
かばんちゃんは火を独占するという意地悪をする鳥(ミミズク)たちから火を奪うのではなく、自ら虫眼鏡を用いて着火することに成功する。

けものフレンズの中では火を起こしたことでかばんちゃんは神話における神と同一の地位にまで上り詰めた。神話においては、動物が独占する火を奪ったり、神から齎されるものであるが、かばんちゃんは自ら火をおこし、「ヒト」としての器用さを見せると同時に、神話的構造に組み込まれたのである。けものフレンズ世界において、かばんちゃんの立ち位置は神話における神々と同様の位置であるのだ。
まとめると、火とは神話において神々や聖なるものから齎される恩寵であった。そしてそれらはしばしば一部の動物たちに独占されていた。それを奪うことで人類は火を手に入れた。神聖な火を自分で起こすなどフレンズは考えられなかった。一方かばんちゃんは鳥たちが独占する火を奪うのではなく、自ら火をつけることで自分自身が神話構造における神や聖なるものの地位まで上り詰めたのと同時に、火を利用する人間としての叡智を見せつけたのであった。かばんちゃんはけものフレンズの世界では神でもあり人でもある。この構造を丹念に描いたけものフレンズ7話は非常に興味深い回であった。
3.調理の意味するところ
先に述べたように動物も自然発生した火を用いて一種の調理をする。しかし、「煮る」行為をするのは人間だけである。そしてうまく火を自由自在に使いこなせるのも人間だけである。
かばんちゃんはカレーを製作していたが、その材料にじゃがいもも存在した。じゃがいも=デンプンの調理は、調理の本質をよく物語っている。デンプンは有史以来ほとんどの時代で人類のエネルギー源であったが加熱調理しないと効率が悪い。加熱すると、デンプンは糖に分解される。じゃがいもを煮るというデンプンの調理は素朴なものに見えて、人類における叡智たる科学的歴史の一分野を飾っているのである。
火はこのようにヒトの持つ叡智を語るのと同時に、社会的なものである。火は原始的な道具では起こすのが大変なので、一度起こした火は大事に保管される(まさしく聖火のように)。このために人は火の番を交代にするようになった。また火には社会的磁力が有る。火は食事をするために必要なので、必然的に人間は決まった時間に決まった場所で(=火の周りで)食事をするようになった。「(火を獲得する前は)集団で食事をする理由はほとんどなかったと考えていいだろう。集めた食べ物はその場で食べることもできたし、隠しておいて好きなときに食べることもできただろう。」*4火は火の周りに共同体を作り上げる機能を齎した。火=調理を中心に人は生活するのである。火による調理は食べ物の価値を押し上げ、食事は犠牲の共有、親睦、儀式の場となった。Focus(フォーカス、中心)という言葉のもともとの意味は「炉」である。人は炉の周りに集うようになったのだ。

焚き火を囲む人々
また、上記に上げた記事で述べる通り、火を用いて発展した食事は食の魔術を生み出した。多くの食べ物は火と結びつき魔術的意味を持った。ガストン・パシュラールはこう回想する。
火は、自然の存在というよりも社会的な存在だ。私は火を食べた。その黄金色を食べ、香りを食べ、ぱちぱちするその音さえも食べていた。(…)火はその人間性を証明する。火はただ焼くだけではなく、ビスケットをさくさくとした食感にし、黄金色にする。火は人間の祝い事に具体的な形を与える。
火と調理は密接に結びついている。 火をうまく扱えるのは人間だけである。調理という集団で行う社会活動は人の特徴である─実際かばんちゃんはサーバルちゃんと共同して調理をした。劇中、鳥たちは調理をかばんちゃんにせがんだ。当たり前であろう、調理とその付随する多くの意味をうまくこなせるのは人の特権なのだ。レヴィ=ストロースは調理には「容器、つまり文化的なものを使う必要がある」と考えた。鍋一つにとっても人間特有の調理の証であり、それは文化的なものなのである。
ここまでを約言すると、火を調理に結びつけてうまく扱えるのは人間だけである。調理は科学的でもあり、また魔術的な意味までを持つ。調理は文化的なものであり、人間の証明でもある。鳥たちがかばんちゃんに調理をお願いしたのも無理がない。調理とは人間性の極限の発露でもあるのだ。
4.おわりに
火と調理という究極的に人間的なものを描いたけものフレンズ7話は傑作であった。かばんちゃんは火を自ら起こし、神となるのと同時に人間であることを証明した。また調理という科学及び文化活動を通して、人間的なものとはいかなるべきかを視聴者に刻みつけた。けものフレンズ7話はこの意味で歴史に残る名作となるであろう。
けものフレンズをまだ見てない皆さんはこちらをどうぞ
5.参考文献
・J.G.フレイザー著『火の起源の神話』
・フェリペ・フェルナンデス=アルメスト『食べる人類誌』
ミリタリーを主題にしたロック・メタル五選
1.はじめに
ロックやメタルには戦争をテーマにした曲が昔からあります。その中でも代表的(と勝手に私が思っている)曲を5つ紹介したいと思います。ミリタリーが好きな方で、ロックやメタルの糸口がわからないという方は好きな戦争をモチーフにした曲から入るのも有りかと思いますので、ぜひ聞いてみてください。
2.戦争をテーマにした曲
Iron Maiden/Aces High
Iron Maiden - Aces High (Official Video)
イギリスの誇るバンド、Iron Maidenの楽曲です。テーマは第2次世界大戦のBoB(バトル・オブ・ブリテン)で、スピットファイアがドイツ軍の機体と戦闘を繰り広げるさまを歌っている。メタルの中でも割りと聞きやすい曲だと思います。
8時方向の敵機は俺達の背後を取った
10機のMe109が太陽から出て来やがる
俺達のスピットファイヤを敵機と反航戦にするため上昇旋回だ
敵機へまっすぐ向かって射撃ボタンを押すんだ
と空戦の熱い戦いを描いていて、テンションがあがる曲なので ぜひ聞いてみてください。『空軍大戦略』を見た後だと更にテンションがぶちあがりますね。
Blue Oyster Cult/ME 262
Blue Oyster Cultは1967年結成のアメリカのハードロックバンド。この曲は曲名を見ればわかるようにドイツ空軍のMe262をテーマにした曲で第三帝国最後の日々のMe262の活躍を歌っています。
ME262はターボジェットの王子
ユンカースJumo004エンジン
機首から放たれるR4Mロケット弾のカルテットの群れ
そして、英語野郎共の飛行機が炎上するのを見るんだ
ああ、お前は私の目撃者。赤色なのは空で
B-17が最後に飛んだとき
それはウェストファーレン上空で、あたりは暗かった
45年4月のことさ
戦争最末期の45年4月の空で戦うMe262の勇姿をこの曲で是非聞きましょう。大戦略などで最終ステージの「ドイツ」などで無限に沸いてくるB-17を相手にした時、または松本零士の『ベルリンの黒騎士』を読んだ時などに聞くと最高です。
Beneth/MG42
Benethハンガリーのブラックメタルバンドで、ドイツ軍に関する曲を幾つか作成しており、その中の一つです。ヒトラーの電動ノコギリとあだ名されたMG42の連射速度の速さを駆け抜けるようなブラストビートで再現しています。
MG42、狂気の武器
群がる敵兵をなぎ倒す、悪魔の武器
どんな奴らも弾の雨には無力
死に物狂いで逃げ惑う奴らに死の鉄槌を
『プライベートライアン』の冒頭の陣地から発射されるMG42の勇姿を見た後に聞くと 最高ですね。みなさんもMG42が敵兵をなぎ倒すシーンを想像しながら聞きましょう。
Sabaton/Screaming Eagles
Sabatonはスウェーデンのメタルバンドで、戦争をテーマにした曲で有名です。どれを選ぶかは悩んだのですが、テーマとして有名なバルジの戦いの中の一つ、バストーニュ包囲戦をテーマにしたこれをチョイスしました。
アーネムへの激しい敗北
彼らは1本の橋を伸ばしすぎている
潮の変わり目だ、敗北しかけている勢いを失い、後退する
バストーニュ地方へ行き、十字路は保持しなければならない
寒い中で一人で歩哨する地面を割る稲妻
砲撃─雷鳴が鳴り響く
バストーニュのナチスの怒り
彼らの力に直面する
曲も歌詞もシンプルなものなので聞きやすいと思います。この曲の他にもSabatonはWW2をモチーフとした多くの曲を作っているので興味があったらぜひ聞いてみてください。個人的には東部戦線での独ソの決戦を描いたPanzerkampfなどがおすすめです。
Marduk/502
Mardukは90年代初頭に結成されたスウェーデンのブラックメタルバンドで時たま戦争を舞台にしたアルバムを作っています。その中の『Panzer Division Marduk』という─アルバム名からミリタリー色が強いのだ─アルバムからの一曲です。
彼らの戦いは永遠に何の記念碑も立たない
そして、ついに彼らの無信仰の幸運は自身を救うことができなかった
弾丸が彼らを殺した時、彼らの運命が決まり
その後、彼らの戦車は彼らの墓になった502 - 餌食の野獣
第502重戦車大隊が撃破した2000の敵戦車
502 - そのツケを払う
502 - 彼らが呼んだ機甲戦で
歌詞を見ればわかるように502はドイツ軍の第502重戦車大隊のことで、歌詞でも彼らの活躍が歌われています。ブラックメタルなので聞きにくいとは思いますが、戦争の狂気さをブラックメタルという荒々しい形で表現する彼らのスタイルはとても好きなので紹介しました。
3.おわりに
ここで紹介したのはほんの一部で他にもあらゆる地域のあらゆる戦闘をテーマにした曲がたくさんあるので、気になった方はいろいろ聞いてみるといいですね。「俺はロックやメタルは聞かない!」という方に少しでもロックやメタルの良さが伝わったらよいのですが、私の文才の無さでそれが全うできるか…ともかく、みなさんも興味があった曲を聞いてみてくださると幸いです。
オカルティズムと「思考の節約」─現代社会におけるステレオタイプの活用
「聞け、驕り高ぶれるアジアとヨーロッパの民よ、
大いなるかたの蜜の声響かせる口を通して、
われわれのことから始めて、わたしが預言せんとするかぎりの全ての真実を。
わたしは虚偽を託宣するフォイボスではない。その者を、愚かな人間どもは神と云い、預言者と詐称したのだ。」
新約聖書の外典『シビュラの託宣』第四巻の有名な出だしであるが、
この外典は一時期、311の予言ではないかと話題になった巻である。
それはこの記述だ。
「地震のために激しく揺れ、諸々の都市がたちまちに倒れる時に。
ロードス人たちにも、最後の、しかし最大の悪がやってくるだろう。
(中略)
おお、リュキアの美しいミュラよ、揺れ動く大地は決しておまえを立たせておきはしない。
まっさかさまに大地に倒れ、寄留者のように、他の地に逃れたいと願うだろう。
それはパタラの不敬虔の上に、ある日、雷霆と地震とともに、海の黒い水が騒乱をまき散らす時である。」
これは直接的には聖書の中の話であるが、いわゆるオカルト信奉者が言うように、聖書は一種抽象的な世界の話であって、アジアに適用することも間違ってはいないかもしれない。
実際、311とこの記述に「類似」している点はある。そしてオカルト信奉者はかかる論を摘出し、文脈をはぎ取ってすぐさま論拠として提示する。
(もちろん、選択的思考と自己欺瞞(self-deception)で脚色されたこれらが論拠とは言えないのは明らかなのだが…。)
しかしここで注目したいのはオカルト野郎はクレイジーだ、という結論ではない。
彼らがオカルトをステレオタイプへの典型的防御手段として使用している点である。
ステレオタイプはWリップマンの指摘以降、悪い風に取られがちだが、
彼は同時に「ステレオタイプは、理解に役立つ」とも述べている。
教養も詰んでこずに、また知識を「得る時間」がないような私のような人間にとって現代社会は甚だ複雑怪奇である。
なぜ飛行機が空を飛ぶのか? これは航空力学を学べば容易に説明できる。
しかしこれを知らないものは「クマバチがなぜ飛ぶかは明らかにされていない。よって飛行機の飛行原理も明らかではない。だから危ない」などという古い論を取り出し、飛行機におびえるのである。
これは未開人が銃を持った西洋人(コンキスタドール)を見て、あいつらは魔術師だ!火を操っている!
などといって恐怖にやられ、国を滅ぼされたのと同じである。
そしてかの311ではかかる未開人的思想とステレオタイプによって防護されている人間が「<自称>情報強者」の中にもい大勢いると実証されてしまった。
先の例を再び取り上げると、彼らは飛行機が飛ぶのは科学で実証できない魔術的なものだと決めつけ、そこで思考停止を起こす。彼らにとって航空力学を学ぶ時間はない。そして私もそうなのだが、学ぶだけの知能もない。
彼らにとって「飛行機が飛ぶ」という現実の出来事を理解する「手助け」となるのがステレオタイプであり、
彼らは一種のステレオタイプ─飛ぶ理由がわかっていないという─を用いて、物事を理解したのである。
このステレオタイプによる理解は、脳の労力的観点から言うとひどく効率がよい。
何か嫌なことがあったら「ユダヤの陰謀」と決めつけたり、何か不思議なことが起きると「魔術だ」などと決めつける。つまり、ステレオタイプによる理解は思考の節約と言っていい現象なのである。
もしここでステレオタイプなき学者が同じ現象を「理解」しようとすればデータの収集、実証など多くの過程を必要とする。
先の飛行機でいえば、飛行機が飛ぶのはまだ解明されていない!と決めつけるのは一瞬だが、「この機体が飛ぶのはエンジンの出力、翼の断面系から計算して求められる揚力、また翼の長さ、そして翼重比を求めだして・・・」などとステレオタイプなしに理解するのは実に時間がかかるし、脳の労力も甚だ大きいものだ。つまり、ひどく労力を使うのだ。
この現象はそのまま311以降広まったデマにも当てはめることができる。地盤などのデータを収集し、計算するのではなしに、「地震兵器の仕業だ!」とステレオタイプで決めつけ、脳を「疲れさせずに」物事を理解した彼ら。
新約聖書の外典に書かれているから311が起きるのは必然だったと決めつける彼ら。
彼らはまさにステレオタイプの奴隷である。しかし、一方で彼らは偉い学者たちがするように脳を「疲れさせることなしに」、思考の節約によって物事を理解できる、ある意味賢い人間だということもできる。
これらの現象はオカルト以外にも数多く現れている。
例えば福島の放射線量に対するステレオタイプ、外国に対するステレオタイプ等々、数を上げれば限りないのだ。
自ら考えることなしに、ステレオタイプで物事を理解しようとする彼らは実は「時代に適した」人間なのかもしれない。
なぜならば、複雑化した現代社会で全てを把握するのは不可能だ。思考の節約により、なるべく頭を働かせずに理解することで我々はなんとか毎日を送っている。もし、君があらゆる現象を理解して行動しようと思えば脳科学から理論物理学まで、ありとあらゆる学問が必要になるのは目に見えている。それを必要としなくて済むのは、我々の見る世界がステレオタイプで塗り固められており、そして思考の節約により考えなくて済むようになっているからだ。もし、君がステレオタイプなしに生きていると思うのならば、それは誤りである。人は必ずステレオタイプの中で生きているのだ。例えば、あの国は◯◯だ、という際に思い浮かぶ「国」はステレオタイプの中の国であることが多い。台湾であれば、台湾という国の実際を知らずに人は「親日」というステレオタイプで見る。もしステレオタイプなしに台湾を見れば、君は台湾がどのような国かに対する処理する情報の多さに苦戦するだろう。このように我々は常にステレオタイプとともにあるのだ。
我々は─それが偉い学者であっても─常に思考の節約により思考をしないように、脳を使わないように生活するようにできている。それがあるからこそ、現代社会で生きていけるのだが、一方でそれは弊害にもなる。少なくとも「我々はステレオタイプの中に生きている」という自覚だけは忘れないほうがいいだろう。
カニバリズムとその意味─栄養摂取と食の魔術
1.はじめに
「ネーコってコーモリ食べる? ネーコって、コーモリ、食べる?」そのうちどっちがどっち食べるのかわからなくなって。まあほらどちらにしても答えはわからないから、どっちになっても大して変わりないけど。*1
猫はコウモリを、あるいはコウモリは猫を食べないかもしれないが、人は人を食べる。中世末から今に至るまで我々は「食人(カニバリズム)」*2に強い興味を持っている。ウィキペディアに項目があり、事象が列挙されているのもその一例であるし、現代でも食人が絡んだ事件が有ると大騒ぎになる。また、フィクションでも食人にフォーカスされた作品は多い。マルキ・ド・サドやエドガー・アラン・ポーなどがこのような作品を残している。では食人とはいったいなんだったのであろうか。また、食人の意義とはなんなのだろうか。ここでは簡潔に食人について考察したい。
2.四種類の食人
食人と一言に言ってもその内容は単一ではない。具体的には四種類の食事があるだろう。
a.食人をする者たちが組織的に動き、システムとして食人を行う。集団として敵の村などを襲い(戦争を起こし)、その結果「戦利品」としてその肉を食べる。積極的カニバリズムであり、戦争カニバリズムである。具体例としてはアステカ文明における食人が挙げられる。この場合、食人はその民族の文化に組み込まれているといえるだろう。
b.病死した親族などの死体を儀礼的に食べる。この場合、敵の村を襲うなどの積極的な行動は見られずに受動的・平和的なカニバリズムであるといえるし、社会的慣習であり、文化体系の一部分である。
c.特殊状態─飢餓状態─などに陥った場合、発作的にカニバリズムを起こす。具体例ではウルグアイ空軍機571便遭難事故*3が挙げられる。
d.個人がカニバリズムという行為そのものに性的快感を覚え、または人肉を美味しいものと考え、実効する。佐川一政によるパリ人肉事件*4が挙げられる。
この四種類のうち、cとdは考察から省きたい。なぜならcは飢餓状態という特殊状態で突発的に食人を行ったのであり、一回きりの特殊的な行為であり、そこに「文化」はないからだ。彼らにあったのは飢餓感を満たそうとする動物的本能だけであり、個別具体的な検証はできても、総体としての食人文化に迫れるものではない。dも同じく個別的検証は可能であろうが、個人の行った行為であり、文化体系の中の一行為でなく、文化の中の行動として行われた食人としての実態に迫れるものではない。
ここで扱うaとbであるが、これは文化に組み込まれた社会的慣習による行動である。個人の意志ではなく、集団が何回にも渡って行ってきた食人なのである。そこには一定の儀式や儀礼が存在し、集団はそれに則って行う。いわば統制された食人であり、だからこそ探求が可能になるのである。
3.戦争におけるカニバリズム(aの場合)とその消失
先に上げたaのような場合におけるカニバリズムを探求する。戦争において勝利した場合得られるのは捕虜である。この捕虜を食人する文化は数多く有る。トゥビナンバ族*5では、捕虜の肉は余禄の動物性食物として尊ばれた。これらの民族では特に「戦士」となる男と違って動物性食物の分配が少なかった女性にとって食人は重要な栄養摂取源であったことが伺われる。
然れども、戦争カニバリズムにおいて重要なのは食人は第一目的でなかったことだ。つまり、食人を積極的に行うものの、それは第二目的であってあくまで戦争が第一目的であった。これらのカニバリズムはマーヴィン・ハリスによれば「戦争カニバリズムをおこなうひとびとは、人肉を目的とする狩人ではない。かれらは戦士であり、集団間の政治の一表現として、同類の人間を追跡し、殺し、虐待する一連の行為にかかわるのである」。とのことだ。
イロコイ族*6やヒューロン族*7は戦争は男女の捕虜を得るという利益以外に、彼らを村へ連れ帰って虐待するという利益を齎していた。虐待行為は政治的な意味もあるが、実利的な意味もあった。若者の「戦闘訓練」に捕虜を利用したのである。つまり、槍や剣の訓練の標的として彼らを利用していたのだ。木や革でできた「的」とちがって、生きた人間を的に使う訓練はどれほど効率的であったかは想像に難くない。また、もし戦争で捕虜になったら、相手に自分が施したような「仕打ち」を受けることを想像させて戦士としての強度を高めた。捕虜になれば死ぬと教えられた日本兵と同じ構造である。
イロコイ族やヒューロン族が村に連れ帰って拷問し、食人した数はあまりわかっていないが、マーヴィンによれば「それほど多くはなかった」という。理由は、彼らの住んでいた地域は大型狩猟動物が豊富におり、動物性食物に困っていなかったと考えられる身からだ。一方、トゥビナンバ族は状況が間逆であり、動物性食物は不足しており、重要な栄養源の一つであった。しかし動物性食物が不足する状況に置かれれば─つまり遠征して戦っている場合など─イロコイ族やヒューロン族も旺盛な食人欲求を示した。1693年1月19日にスケネクタディー近郊で行われたフランス軍との戦いの後、アルバニー市長のピーター・スカイラーは、味方のイロコイ族が「かれらのもって生まれた野蛮さのゆえに、敵の死体を細切れにして食べた」と報告している。わざわざ味方の野蛮な振る舞いをでっちあげて、ことさらに嘘をつく必要がないため、これは少なくとも部分的に事実であると考えられる。この報告は、事件についてスカイラーにインタビューした、歴史家でニューヨーク州知事キャドワラダー・コルデンによって確認され、文章化されている。
インディアンたちはみつけたフランス兵の死骸を食べた……スカイラーがその時彼らの中に入っていくと、一緒に肉スープを飲まないかと誘われた。何人かが煮ていた。彼は飲んだ。しかし、インディアンが、おかわりを掬おうとして鍋に柄杓を入れると、フランス人の腕が出てきた。その途端、彼の食欲はなくなった。*8
戦死した敵兵を戦地糧食に使うことは、世界各地の村落社会でよく行われていたとマーヴィンは言う。例えばニュージランドのマオリ族の事例から、重要部分について詳しく知ることができる。マオリ族の戦士隊は機動性を高めるために行軍中に人肉を利用した。マオリ族は戦闘が終わるとすぐに、戦死者と、捕まえた捕虜の大部分の両方を(少なからず)食べた。マオリ族の場合、食人は「普段」(非戦争時)はほとんど活用していなかったかもしれないが、戦争中においては貴重な栄養摂取とされていたのは確かだ。

(1577年に描かれたブラジル地域における食人の様子)
さて、ここで述べていた戦争カニバリズムであるが、この実態というのは戦死者を食べる以外には小規模の部族が小規模の部族を襲うにとどまっていた。*9なぜなら彼らは輜重が貧弱で大量の捕虜(あるいは大量の人肉)を拠点まで連れ帰るのは容易ではなかったと考えられるからである。当たり前であるが捕虜の輸送には莫大なコストがかかるのである。大規模な会戦などで敵を打倒した場合などは安心してその場で「調理」を始められるかもしれないが、実際のところ小規模な部族であった彼らの戦争様式というのは村を奇襲で襲い、そして襲われた村の部族は一目散に森へ─おそらく避難地点や結集地点があったのだろう─逃げ込むことだった。うかうかしていれば、このように結集して兵力を立て直した敵部族に反撃される可能性があった。大量の捕虜や人肉は機動力を活かしてヒットアンドアウェイをするに従って最も大事となる機動力を大幅に削ぐことになる。そのため獲得できる捕虜=人肉としても少量であったことが伺われる。
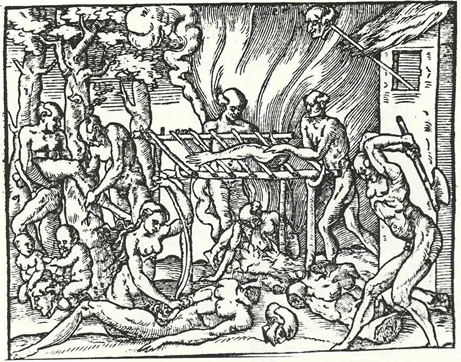
(16世紀に描かれたネイティブ・アメリカンによる食人行為)
この考えで行けば大規模な会戦を行えるだけの兵力を持つ「国家」は食人を更に推し進めるかもしれない、と考えられる。しかし食人行動は国家が大規模になるほど現れなくなってくるのは世界史を学んだ諸君らにはわかるだろう。これはどういうことだろうか。
これらに関してマーヴィンはある予想をしている。それによれば部族社会は大量の余剰生産物を生産できないため、捕虜を養えない。また、環境から捕虜を活かせる労働などがない。国家の人口が多くなればなるほど、余剰生産物は増え、捕虜を活かせる労働が─例えば大規模な農業など─発生してくる。部族社会では得た捕虜(活用のしようがない)を殺して食べるのは合理的である。しかし国家ともなれば、得た捕虜を労働させて生産物を生み出し、それを消費するほうが長期的に利益となる……彼はそう予想している。また、食料の補給に関しても、「戦闘に勝って初めてできる食人」より、一定の水準を必ず確保できる後方からの輸送・豊かな村での徴発に頼るのが当然効果的である。これらの要因から国家が大きくなればなるほど食人行動は─儀礼的な意味を大きく持つ食人を除いて─減ったのだと考えられる。
また、食人を禁止することは別のベネフィットを生み出した。敵国家に降伏しても食人されないという安心である。「お前たちを食うためにやってきた」と自称する国家よりも「お前たちを文明化するためにやってきた」と自称する国家のほうが大義名分として帝国主義的な政策は取りやすいし支配地域にも受け入れられやすい。ローマ帝国がそうだが、文明化の旗印の下、蛮族を討つのである。このような図式は野蛮な民族を教化するという大正義の下行われるのであり、兵士たちの士気も「食人のため」より高まることとなった。そうとなれば、この「食人をしない」という大前提を守るために食人を禁止に追いやることの意味がわかるだろう。なぜ今の我々は近親者の死体でも食人をしないか。
人肉食の禁止から外れることは、どんなことでもあろうと、国家の戦争カニバリズム撲滅の公約をあやうくするものとのなる。国家は、人民に死んだ敵を食べるのを禁じながら、死んだ近親者を食べるのは許すなど、どうしてできよう。旧世界では、馬がそうであるように、人間はそれが生きていようと死んでいようと、味方であろうと敵であろうと、どんなに殺すに良いものであっても、食べるにはよくないものとみなされるようになったのである。*10
つまり、総体的に見れば、我々は食人をするより、食人をしないほうが利益を得られるようになった、ということになる。捕虜の肉を食べるより、その捕虜を納税者・農民・労働者としたほうが価値があるようになったのであり、また国家のモラルと言った面でも食人をしないのが有利となったのである。
逆に言えば、国家が政治的・経済的に捕虜を取るより食人に回したほうがベネフィットを得られると判断したらその国では食人が行われる可能性がある。強大な帝国を築いていながらも、食人を行ったアステカ文明がこの例である。「(アステカ文明の)一人あたりの獣肉、魚、鶏肉摂取量は、一日に数グラムにもならなかった」。極度の動物性食物の不足はより強い食人欲求を生み出し、国家の司令官が部下に食人をやめるようにいうのは、大型狩猟動物や家畜がいた旧世界よりも遥かに困難だっただろう。このような状況では、食人は直接的に「栄養摂取」の欲求を満たすただひとつの解決方法だったのである。このような場合、食人を禁止する政治的利点は薄れ、結果としてトゥビナンバ族やイロコイ族のような社会に近い結果となった。これと似たようなものとして「海の慣習」がある。遭難したり難破した際に乗組員の死体を食べて良いとする慣習であり、1710年にノッティンガム・ガレー号の遭難では実際に食人は行われた。船といういわば「小国家」の中では食人を禁止して政治的利点─モラルの崩壊を防ぐ─より実利的な栄養摂取の利点が勝ったということである。
ただし、アステカ文明の食人は後述する「儀礼的な意味」を他の部族より遥かに多く残していたのは考慮すべきである。約言すれば、彼らは肉がないから人を食べた、と一言で言うことはできない。もちろんそれも一つの要因であるのだが、そこには魔術的・儀礼的意味も多分に含まれていたのである。
4.平和的なカニバリズム(bの場合)と食の魔術
パプア高地のギミ族の女性はかつて、男たちが死ぬとその死体を食べていた。この風習は1960年代までつづき、いまでも人形を死体に見立てて食べるふりをすることで再現されている。また、南アメリカのオリノコ川に村を作るギアカ族でも死者を火葬し、その骨、半ば炭化した骨を集めて木製の臼でひき、それを近親者がバナナのスープに入れて、儀式の際に飲むとされている。
さて、これらのカニバリズムは栄養摂取以外の目的があるのが明らかだ。炭化した骨で動物性食物を摂取したことにならない。なにか別の目的が有るのだ。ここで出てくるのが私が先にブログで書いた「食の魔術」である(詳しくは下記参照のこと)
食の魔術とは食べ物に栄養摂取以外の目的を求めることだ。例えば水素水は合理的に考えれば、水分摂取以外の「栄養学的意味」を持たない。しかし人々は健康を願って飲む。そこに科学的なものは存在しない。あるのは食に栄養摂取以外の─しばしば非科学的な─意味を求めるという行為である。食とは生きるためだけに食べているのではない。食べることは魔術的な意味を持つのである。それは水素水の謳う科学的ではない効果を見ればわかるだろう。食とは多くの(ともすれば魔術的な)意味を秘めているのである。
食人はこの食の魔術に大きく影響を受けている。例えば、パプアのオロカイバ族は、食人は死んだ戦士の代償として霊魂を捉える方法だとされている。オナバスル族にとって食人対象は魔女とされた人間だけであった。先に述べたアステカ文明では食人は栄養摂取以外に、「勇敢な敵戦士の魂を得る」方法とされていた。フィジーでも食人は行われ、食べた分だけその記録として石をおいていった。だがそうやって石をおいて「記念する」という行為自体が、カニバリズムが通常の家畜を食べる行為と一線を画す行為なのがわかる。フィジーでは食人は支配を象徴するものであって、食べることで自らの地位を誇っていたのだ。また、フィクションでは食人種の食べ物(人肉)を味見したシンドバッドの仲間たちは(食人によって)狂ったのである。これも非科学的な、魔術的な食の魔術の存在を感じさせる。
食人とは栄養摂取の意味だけではなかった。そこに食の魔術があったのだ。死んだ戦士の力を取り入れ、悪魔を遠ざけ、肉をみんなで食らうことで絆を作り、また自らの支配体系を示す。これは今の食事にも当てはまることだ。フェリペ・フェルナンデス=アルメストによれば「食人種からホメオパシー支持者や健康食品愛好家に至るまで、みな自分の人格を磨き、力を伸ばし、寿命を伸ばすのに役立つと思われる食べ物を食べているのである」。戦争カニバリズムにおいてもこれらは変わらない。敵兵士の肉を食べるのは魂を取り入れる儀礼・儀式でもあったのだ。これらは表裏一体で切り離すことができない。一方ではタンパク質摂取のためであり、一方では食の魔術のためであった。これらを切り離して一方的な考えで物事を見ることはできない。
5.終わりに
これまで述べてきたように、カニバリズムとは動物性食物の摂取と食の魔術の二本柱によって成り立っていた行為であった。現代の我々から見ると食人行為はおぞましく、大変恐ろしいものに思える。しかし、食人種が恐れをなすほどの大戦争を繰り広げ、食人種が食べてきた人間より多くの人間を砲弾・銃弾・爆弾で殺してきた我々と比べてどこがおぞましいのだろうか。捕虜の首を切り落とすのと、WW2東部戦線でよく見られたように捕虜をその場で銃殺したり、または収容所でおぞましく餓死・病死させる行為のどちらが恐ろしいのだろうか。カニバリズムは確かに実在した。しかしそれをことさら大げさに取り扱って、我々「近代人」がその近代に何をしてきたかを考えないのは語るに落ちるのである。
ここまで著述した食人に関する考察はかなり断片的で曖昧なものだというのをご容赦していただきたい。もっと食人を行っていた部族は存在するし(例えばニューギニアにおける食人などが有名である)、その意味(食の魔術)も様々である。しかし私の知識不足でかなり限定的な考察になったのは否めない。誰か知識の有る方がこのテーマについてもっと詳しく研究してくださるといいのだが……。
余談になるが、イラク戦争において米軍兵士が食人を行ったと『History Today』においてリチャード・サッグ氏は述べている。これによれば敵兵士の死体を食べることは「復讐」として行われたそうだが、これも食の魔術の一環と言えるだろう。死体を食べて復讐をするという意味を食人に見出していたのだから。これと似た事例で中国の文化大革命において復讐として(政治的な)敵の死体を食べた事例もあげられるのである。現在でも我々は食の魔術とその極地たる食人から逃れることはできなそうだ……。
参考文献
・フェリペ・フェルナンデス=アルメスト著『食べる人類誌』
・マーヴィン・ハリス著『食と文化の謎』
・同上『ヒトはなぜヒトを食べたか―生態人類学から見た文化の起源』
*2:ここで先に述べておきたいのだが、カニバリズムは実在した。しかしその実態というのは多くが誇張されているということだ。植民地拡大期に未開の国の部族を全て食人種にすることは多々あった。Man Eating Mythとも言うがとにかくその時代に書かれたのは虚偽だらけの文献も多い。
*3:ウルグアイ空軍571便が墜落し生存者たちが飢えを満たすために食人を行った事件
*4:1981年、パリに留学していた佐川一政が友人の女性を射殺し、死姦した上で食した事件
*5:南アメリカ、ブラジルのアマゾン河口からサン・パウロ州までの海岸部と内陸部に広く住んでいたトゥピ系の先住民
*6:1570年頃、現在のニューヨーク州中央部に住んでいた5つのインディアンの民族が結成した連盟組織の部族を指す言葉
*7:北アメリカ,五大湖の一つヒューロン湖周辺に居住するアメリカインディアンの一民族。ヒューロンはフランス語で剛毛の頭,ないし悪漢の意。自称ベンダットまたはワンダット
*9:これらの戦争形態は当時の状況に依存する。当時、彼らは村単位の小規模部族であり、狩猟に生活を頼っていた。このような状況で最も多くの「食」を得られるのは狩猟場における人口圧をなるべく削減することであった。競争者がいなくなれば、その分多くの食料を得られるのである。そのために相手の人口圧を減らすことができる小規模な戦争は実利的な意味合いを持っていた
*10:同上
