カニバリズムとその意味─栄養摂取と食の魔術
1.はじめに
「ネーコってコーモリ食べる? ネーコって、コーモリ、食べる?」そのうちどっちがどっち食べるのかわからなくなって。まあほらどちらにしても答えはわからないから、どっちになっても大して変わりないけど。*1
猫はコウモリを、あるいはコウモリは猫を食べないかもしれないが、人は人を食べる。中世末から今に至るまで我々は「食人(カニバリズム)」*2に強い興味を持っている。ウィキペディアに項目があり、事象が列挙されているのもその一例であるし、現代でも食人が絡んだ事件が有ると大騒ぎになる。また、フィクションでも食人にフォーカスされた作品は多い。マルキ・ド・サドやエドガー・アラン・ポーなどがこのような作品を残している。では食人とはいったいなんだったのであろうか。また、食人の意義とはなんなのだろうか。ここでは簡潔に食人について考察したい。
2.四種類の食人
食人と一言に言ってもその内容は単一ではない。具体的には四種類の食事があるだろう。
a.食人をする者たちが組織的に動き、システムとして食人を行う。集団として敵の村などを襲い(戦争を起こし)、その結果「戦利品」としてその肉を食べる。積極的カニバリズムであり、戦争カニバリズムである。具体例としてはアステカ文明における食人が挙げられる。この場合、食人はその民族の文化に組み込まれているといえるだろう。
b.病死した親族などの死体を儀礼的に食べる。この場合、敵の村を襲うなどの積極的な行動は見られずに受動的・平和的なカニバリズムであるといえるし、社会的慣習であり、文化体系の一部分である。
c.特殊状態─飢餓状態─などに陥った場合、発作的にカニバリズムを起こす。具体例ではウルグアイ空軍機571便遭難事故*3が挙げられる。
d.個人がカニバリズムという行為そのものに性的快感を覚え、または人肉を美味しいものと考え、実効する。佐川一政によるパリ人肉事件*4が挙げられる。
この四種類のうち、cとdは考察から省きたい。なぜならcは飢餓状態という特殊状態で突発的に食人を行ったのであり、一回きりの特殊的な行為であり、そこに「文化」はないからだ。彼らにあったのは飢餓感を満たそうとする動物的本能だけであり、個別具体的な検証はできても、総体としての食人文化に迫れるものではない。dも同じく個別的検証は可能であろうが、個人の行った行為であり、文化体系の中の一行為でなく、文化の中の行動として行われた食人としての実態に迫れるものではない。
ここで扱うaとbであるが、これは文化に組み込まれた社会的慣習による行動である。個人の意志ではなく、集団が何回にも渡って行ってきた食人なのである。そこには一定の儀式や儀礼が存在し、集団はそれに則って行う。いわば統制された食人であり、だからこそ探求が可能になるのである。
3.戦争におけるカニバリズム(aの場合)とその消失
先に上げたaのような場合におけるカニバリズムを探求する。戦争において勝利した場合得られるのは捕虜である。この捕虜を食人する文化は数多く有る。トゥビナンバ族*5では、捕虜の肉は余禄の動物性食物として尊ばれた。これらの民族では特に「戦士」となる男と違って動物性食物の分配が少なかった女性にとって食人は重要な栄養摂取源であったことが伺われる。
然れども、戦争カニバリズムにおいて重要なのは食人は第一目的でなかったことだ。つまり、食人を積極的に行うものの、それは第二目的であってあくまで戦争が第一目的であった。これらのカニバリズムはマーヴィン・ハリスによれば「戦争カニバリズムをおこなうひとびとは、人肉を目的とする狩人ではない。かれらは戦士であり、集団間の政治の一表現として、同類の人間を追跡し、殺し、虐待する一連の行為にかかわるのである」。とのことだ。
イロコイ族*6やヒューロン族*7は戦争は男女の捕虜を得るという利益以外に、彼らを村へ連れ帰って虐待するという利益を齎していた。虐待行為は政治的な意味もあるが、実利的な意味もあった。若者の「戦闘訓練」に捕虜を利用したのである。つまり、槍や剣の訓練の標的として彼らを利用していたのだ。木や革でできた「的」とちがって、生きた人間を的に使う訓練はどれほど効率的であったかは想像に難くない。また、もし戦争で捕虜になったら、相手に自分が施したような「仕打ち」を受けることを想像させて戦士としての強度を高めた。捕虜になれば死ぬと教えられた日本兵と同じ構造である。
イロコイ族やヒューロン族が村に連れ帰って拷問し、食人した数はあまりわかっていないが、マーヴィンによれば「それほど多くはなかった」という。理由は、彼らの住んでいた地域は大型狩猟動物が豊富におり、動物性食物に困っていなかったと考えられる身からだ。一方、トゥビナンバ族は状況が間逆であり、動物性食物は不足しており、重要な栄養源の一つであった。しかし動物性食物が不足する状況に置かれれば─つまり遠征して戦っている場合など─イロコイ族やヒューロン族も旺盛な食人欲求を示した。1693年1月19日にスケネクタディー近郊で行われたフランス軍との戦いの後、アルバニー市長のピーター・スカイラーは、味方のイロコイ族が「かれらのもって生まれた野蛮さのゆえに、敵の死体を細切れにして食べた」と報告している。わざわざ味方の野蛮な振る舞いをでっちあげて、ことさらに嘘をつく必要がないため、これは少なくとも部分的に事実であると考えられる。この報告は、事件についてスカイラーにインタビューした、歴史家でニューヨーク州知事キャドワラダー・コルデンによって確認され、文章化されている。
インディアンたちはみつけたフランス兵の死骸を食べた……スカイラーがその時彼らの中に入っていくと、一緒に肉スープを飲まないかと誘われた。何人かが煮ていた。彼は飲んだ。しかし、インディアンが、おかわりを掬おうとして鍋に柄杓を入れると、フランス人の腕が出てきた。その途端、彼の食欲はなくなった。*8
戦死した敵兵を戦地糧食に使うことは、世界各地の村落社会でよく行われていたとマーヴィンは言う。例えばニュージランドのマオリ族の事例から、重要部分について詳しく知ることができる。マオリ族の戦士隊は機動性を高めるために行軍中に人肉を利用した。マオリ族は戦闘が終わるとすぐに、戦死者と、捕まえた捕虜の大部分の両方を(少なからず)食べた。マオリ族の場合、食人は「普段」(非戦争時)はほとんど活用していなかったかもしれないが、戦争中においては貴重な栄養摂取とされていたのは確かだ。

(1577年に描かれたブラジル地域における食人の様子)
さて、ここで述べていた戦争カニバリズムであるが、この実態というのは戦死者を食べる以外には小規模の部族が小規模の部族を襲うにとどまっていた。*9なぜなら彼らは輜重が貧弱で大量の捕虜(あるいは大量の人肉)を拠点まで連れ帰るのは容易ではなかったと考えられるからである。当たり前であるが捕虜の輸送には莫大なコストがかかるのである。大規模な会戦などで敵を打倒した場合などは安心してその場で「調理」を始められるかもしれないが、実際のところ小規模な部族であった彼らの戦争様式というのは村を奇襲で襲い、そして襲われた村の部族は一目散に森へ─おそらく避難地点や結集地点があったのだろう─逃げ込むことだった。うかうかしていれば、このように結集して兵力を立て直した敵部族に反撃される可能性があった。大量の捕虜や人肉は機動力を活かしてヒットアンドアウェイをするに従って最も大事となる機動力を大幅に削ぐことになる。そのため獲得できる捕虜=人肉としても少量であったことが伺われる。
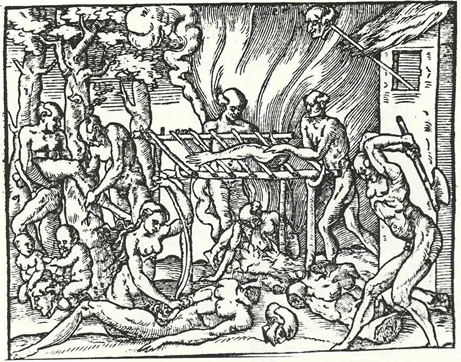
(16世紀に描かれたネイティブ・アメリカンによる食人行為)
この考えで行けば大規模な会戦を行えるだけの兵力を持つ「国家」は食人を更に推し進めるかもしれない、と考えられる。しかし食人行動は国家が大規模になるほど現れなくなってくるのは世界史を学んだ諸君らにはわかるだろう。これはどういうことだろうか。
これらに関してマーヴィンはある予想をしている。それによれば部族社会は大量の余剰生産物を生産できないため、捕虜を養えない。また、環境から捕虜を活かせる労働などがない。国家の人口が多くなればなるほど、余剰生産物は増え、捕虜を活かせる労働が─例えば大規模な農業など─発生してくる。部族社会では得た捕虜(活用のしようがない)を殺して食べるのは合理的である。しかし国家ともなれば、得た捕虜を労働させて生産物を生み出し、それを消費するほうが長期的に利益となる……彼はそう予想している。また、食料の補給に関しても、「戦闘に勝って初めてできる食人」より、一定の水準を必ず確保できる後方からの輸送・豊かな村での徴発に頼るのが当然効果的である。これらの要因から国家が大きくなればなるほど食人行動は─儀礼的な意味を大きく持つ食人を除いて─減ったのだと考えられる。
また、食人を禁止することは別のベネフィットを生み出した。敵国家に降伏しても食人されないという安心である。「お前たちを食うためにやってきた」と自称する国家よりも「お前たちを文明化するためにやってきた」と自称する国家のほうが大義名分として帝国主義的な政策は取りやすいし支配地域にも受け入れられやすい。ローマ帝国がそうだが、文明化の旗印の下、蛮族を討つのである。このような図式は野蛮な民族を教化するという大正義の下行われるのであり、兵士たちの士気も「食人のため」より高まることとなった。そうとなれば、この「食人をしない」という大前提を守るために食人を禁止に追いやることの意味がわかるだろう。なぜ今の我々は近親者の死体でも食人をしないか。
人肉食の禁止から外れることは、どんなことでもあろうと、国家の戦争カニバリズム撲滅の公約をあやうくするものとのなる。国家は、人民に死んだ敵を食べるのを禁じながら、死んだ近親者を食べるのは許すなど、どうしてできよう。旧世界では、馬がそうであるように、人間はそれが生きていようと死んでいようと、味方であろうと敵であろうと、どんなに殺すに良いものであっても、食べるにはよくないものとみなされるようになったのである。*10
つまり、総体的に見れば、我々は食人をするより、食人をしないほうが利益を得られるようになった、ということになる。捕虜の肉を食べるより、その捕虜を納税者・農民・労働者としたほうが価値があるようになったのであり、また国家のモラルと言った面でも食人をしないのが有利となったのである。
逆に言えば、国家が政治的・経済的に捕虜を取るより食人に回したほうがベネフィットを得られると判断したらその国では食人が行われる可能性がある。強大な帝国を築いていながらも、食人を行ったアステカ文明がこの例である。「(アステカ文明の)一人あたりの獣肉、魚、鶏肉摂取量は、一日に数グラムにもならなかった」。極度の動物性食物の不足はより強い食人欲求を生み出し、国家の司令官が部下に食人をやめるようにいうのは、大型狩猟動物や家畜がいた旧世界よりも遥かに困難だっただろう。このような状況では、食人は直接的に「栄養摂取」の欲求を満たすただひとつの解決方法だったのである。このような場合、食人を禁止する政治的利点は薄れ、結果としてトゥビナンバ族やイロコイ族のような社会に近い結果となった。これと似たようなものとして「海の慣習」がある。遭難したり難破した際に乗組員の死体を食べて良いとする慣習であり、1710年にノッティンガム・ガレー号の遭難では実際に食人は行われた。船といういわば「小国家」の中では食人を禁止して政治的利点─モラルの崩壊を防ぐ─より実利的な栄養摂取の利点が勝ったということである。
ただし、アステカ文明の食人は後述する「儀礼的な意味」を他の部族より遥かに多く残していたのは考慮すべきである。約言すれば、彼らは肉がないから人を食べた、と一言で言うことはできない。もちろんそれも一つの要因であるのだが、そこには魔術的・儀礼的意味も多分に含まれていたのである。
4.平和的なカニバリズム(bの場合)と食の魔術
パプア高地のギミ族の女性はかつて、男たちが死ぬとその死体を食べていた。この風習は1960年代までつづき、いまでも人形を死体に見立てて食べるふりをすることで再現されている。また、南アメリカのオリノコ川に村を作るギアカ族でも死者を火葬し、その骨、半ば炭化した骨を集めて木製の臼でひき、それを近親者がバナナのスープに入れて、儀式の際に飲むとされている。
さて、これらのカニバリズムは栄養摂取以外の目的があるのが明らかだ。炭化した骨で動物性食物を摂取したことにならない。なにか別の目的が有るのだ。ここで出てくるのが私が先にブログで書いた「食の魔術」である(詳しくは下記参照のこと)
食の魔術とは食べ物に栄養摂取以外の目的を求めることだ。例えば水素水は合理的に考えれば、水分摂取以外の「栄養学的意味」を持たない。しかし人々は健康を願って飲む。そこに科学的なものは存在しない。あるのは食に栄養摂取以外の─しばしば非科学的な─意味を求めるという行為である。食とは生きるためだけに食べているのではない。食べることは魔術的な意味を持つのである。それは水素水の謳う科学的ではない効果を見ればわかるだろう。食とは多くの(ともすれば魔術的な)意味を秘めているのである。
食人はこの食の魔術に大きく影響を受けている。例えば、パプアのオロカイバ族は、食人は死んだ戦士の代償として霊魂を捉える方法だとされている。オナバスル族にとって食人対象は魔女とされた人間だけであった。先に述べたアステカ文明では食人は栄養摂取以外に、「勇敢な敵戦士の魂を得る」方法とされていた。フィジーでも食人は行われ、食べた分だけその記録として石をおいていった。だがそうやって石をおいて「記念する」という行為自体が、カニバリズムが通常の家畜を食べる行為と一線を画す行為なのがわかる。フィジーでは食人は支配を象徴するものであって、食べることで自らの地位を誇っていたのだ。また、フィクションでは食人種の食べ物(人肉)を味見したシンドバッドの仲間たちは(食人によって)狂ったのである。これも非科学的な、魔術的な食の魔術の存在を感じさせる。
食人とは栄養摂取の意味だけではなかった。そこに食の魔術があったのだ。死んだ戦士の力を取り入れ、悪魔を遠ざけ、肉をみんなで食らうことで絆を作り、また自らの支配体系を示す。これは今の食事にも当てはまることだ。フェリペ・フェルナンデス=アルメストによれば「食人種からホメオパシー支持者や健康食品愛好家に至るまで、みな自分の人格を磨き、力を伸ばし、寿命を伸ばすのに役立つと思われる食べ物を食べているのである」。戦争カニバリズムにおいてもこれらは変わらない。敵兵士の肉を食べるのは魂を取り入れる儀礼・儀式でもあったのだ。これらは表裏一体で切り離すことができない。一方ではタンパク質摂取のためであり、一方では食の魔術のためであった。これらを切り離して一方的な考えで物事を見ることはできない。
5.終わりに
これまで述べてきたように、カニバリズムとは動物性食物の摂取と食の魔術の二本柱によって成り立っていた行為であった。現代の我々から見ると食人行為はおぞましく、大変恐ろしいものに思える。しかし、食人種が恐れをなすほどの大戦争を繰り広げ、食人種が食べてきた人間より多くの人間を砲弾・銃弾・爆弾で殺してきた我々と比べてどこがおぞましいのだろうか。捕虜の首を切り落とすのと、WW2東部戦線でよく見られたように捕虜をその場で銃殺したり、または収容所でおぞましく餓死・病死させる行為のどちらが恐ろしいのだろうか。カニバリズムは確かに実在した。しかしそれをことさら大げさに取り扱って、我々「近代人」がその近代に何をしてきたかを考えないのは語るに落ちるのである。
ここまで著述した食人に関する考察はかなり断片的で曖昧なものだというのをご容赦していただきたい。もっと食人を行っていた部族は存在するし(例えばニューギニアにおける食人などが有名である)、その意味(食の魔術)も様々である。しかし私の知識不足でかなり限定的な考察になったのは否めない。誰か知識の有る方がこのテーマについてもっと詳しく研究してくださるといいのだが……。
余談になるが、イラク戦争において米軍兵士が食人を行ったと『History Today』においてリチャード・サッグ氏は述べている。これによれば敵兵士の死体を食べることは「復讐」として行われたそうだが、これも食の魔術の一環と言えるだろう。死体を食べて復讐をするという意味を食人に見出していたのだから。これと似た事例で中国の文化大革命において復讐として(政治的な)敵の死体を食べた事例もあげられるのである。現在でも我々は食の魔術とその極地たる食人から逃れることはできなそうだ……。
参考文献
・フェリペ・フェルナンデス=アルメスト著『食べる人類誌』
・マーヴィン・ハリス著『食と文化の謎』
・同上『ヒトはなぜヒトを食べたか―生態人類学から見た文化の起源』
*2:ここで先に述べておきたいのだが、カニバリズムは実在した。しかしその実態というのは多くが誇張されているということだ。植民地拡大期に未開の国の部族を全て食人種にすることは多々あった。Man Eating Mythとも言うがとにかくその時代に書かれたのは虚偽だらけの文献も多い。
*3:ウルグアイ空軍571便が墜落し生存者たちが飢えを満たすために食人を行った事件
*4:1981年、パリに留学していた佐川一政が友人の女性を射殺し、死姦した上で食した事件
*5:南アメリカ、ブラジルのアマゾン河口からサン・パウロ州までの海岸部と内陸部に広く住んでいたトゥピ系の先住民
*6:1570年頃、現在のニューヨーク州中央部に住んでいた5つのインディアンの民族が結成した連盟組織の部族を指す言葉
*7:北アメリカ,五大湖の一つヒューロン湖周辺に居住するアメリカインディアンの一民族。ヒューロンはフランス語で剛毛の頭,ないし悪漢の意。自称ベンダットまたはワンダット
*9:これらの戦争形態は当時の状況に依存する。当時、彼らは村単位の小規模部族であり、狩猟に生活を頼っていた。このような状況で最も多くの「食」を得られるのは狩猟場における人口圧をなるべく削減することであった。競争者がいなくなれば、その分多くの食料を得られるのである。そのために相手の人口圧を減らすことができる小規模な戦争は実利的な意味合いを持っていた
*10:同上